※記事内に広告を含む場合があります
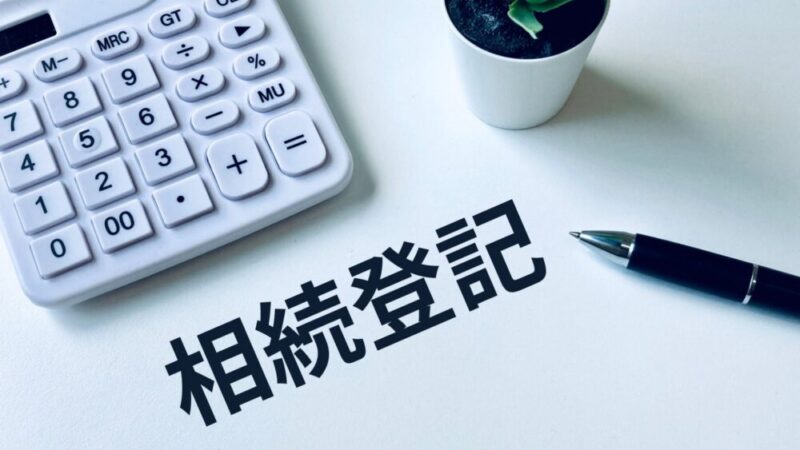
不動産(土地、建物)の所有者が亡くなった場合など相続が発生した際は不動産の名義変更が必要です。不動産の名義変更手続きのことを相続登記と呼びます。相続登記について、詳細を把握している人は少ないです。
この記事では、相続登記の基本から費用、手続きの方法などをわかりやすく解説します。記事を読むと、スムーズに相続登記の手続きができるようになり、無駄な出費を避けられます。
相続登記の基礎知識

相続登記とは、個人が所有していた不動産を相続人の名義に変更する手続きです。
相続登記の基礎知識について、以下の3つを解説します。
- 相続登記の目的
- 相続登記の義務化の背景
- 相続登記の手続きの流れ
相続登記の目的
相続登記の目的は、所有権の移転を正確に記録し、不動産の所有者を明確にすることです。
相続登記することで、以下の効果が期待できます。
- 相続人の権利を明確にする
- 将来の取引がスムーズになる
- 相続争いを防止する
- 行政上の手続きがスムーズになる
相続登記の義務化の背景

不動産の所有権の正確な記録を促進し、不動産取引の透明性を高めることが目的です。2024年4月より相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
相続登記の義務化は、法的なトラブルや相続争いの発生を未然に防ぐことを目的としています。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となるので、注意が必要です。
相続登記の手続きの流れ
相続登記の具体的な流れは以下のとおりです。
- 必要書類を集める
- 相続人全員の同意を形成する
- 不動産の詳細を把握する
- 相続に関する申述書類を作成する
- 法務局で登記申請する
- 登記完了の確認をする
相続登記の手続きは複雑なため、スムーズに進んでも3カ月程度はかかります。相続人間での同意が得られない場合や複数の不動産が対象の場合には、数年かかるケースも多いです。
相続登記にかかる費用

相続登記にかかる費用について、以下の3つを解説します。
- 相続登記の費用の範囲
- 相続登記の費用が異なる理由
- 相続登記の主要な費用の内訳
費用を把握しておくことで、相続が発生した際に慌てずに対応できます。
相続登記の費用の範囲
相続登記にかかる費用は、一般的に10~30万円程度です。地域や不動産の価値、手続きの複雑さによって費用は変動します。予想外の追加費用が発生する場合もあるため、事前に複数の司法書士から見積もりを取り、無駄な出費を避けることが重要です。
相続登記の費用が異なる理由

相続登記の費用が変化する理由は以下のとおりです。
- 不動産の種類、価値、所在地
- 手続きに必要となる書類
- 司法書士や弁護士など専門家の違い
- 相続人の数や状況
手続きが複雑になるほど費用が増加するのが一般的です。
相続登記の主要な費用の内訳
相続登記で必要になる費用は以下のとおりです。
- 司法書士の報酬
- 登録免許税
- 必要書類の取得費用
- 地図・図面の作成費用
- その他の諸経費(郵送費、交通費等)
事前に必要な費用をよく確認して、予想外の出費を防ぎましょう。
相続登記にかかる費用の詳細
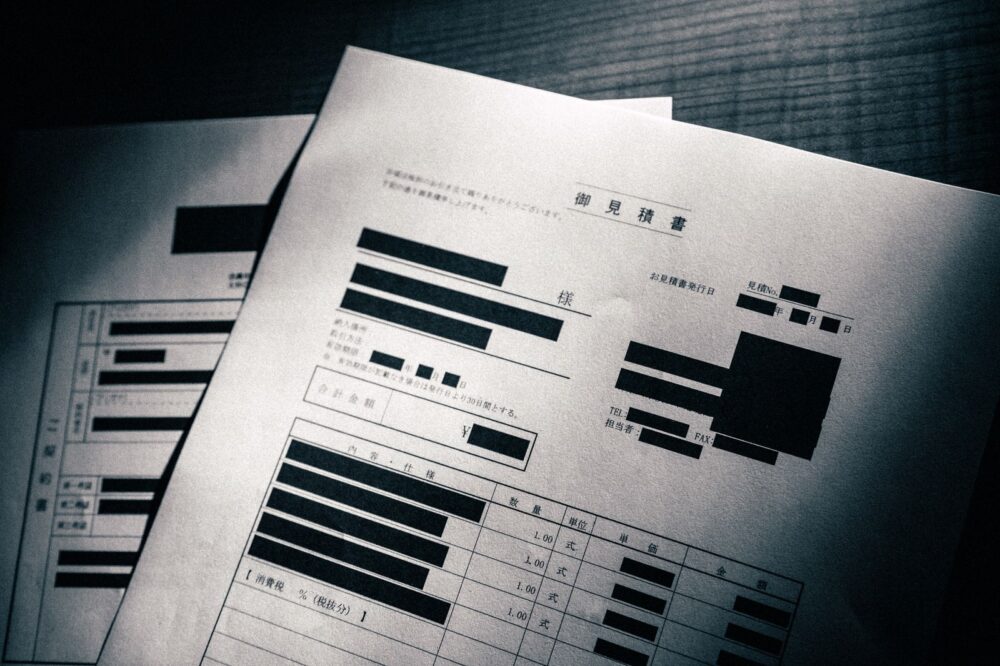
相続登記の以下の費用について解説します。
- 必要書類の取得費用
- 登録免許税
- 司法書士の報酬
必要書類の取得費用
主な必要書類と費用の相場は、以下のとおりです。
- 戸籍謄本や戸籍抄本:1通あたり450円程度
- 住民票:1通あたり300円程度
- 不動産登記簿謄本:1通あたり600円程度
- 遺産分割協議書:変動あり(専門家に依頼した場合は追加費用が必要)
- 印紙代:登録免許税の金額による
特に取得が大変なのが、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」です。複数回の転籍を繰り返している場合、多くの戸籍謄本が必要になります。
また、2024年3月より戸籍謄本は本籍地以外の市区町村役場でも取得できるようになりました。本人または同一戸籍の親族(配偶者、父母、祖父母、子、孫)の本籍地が遠方でも、最寄りの市区町村役場の窓口で取得可能です。
ただし、傍系親族(兄弟姉妹、従兄弟、叔父、叔母)の戸籍謄本の取得には本人からの委任状が必要になることも覚えておきましょう。
※コンピューター化されていない戸籍謄本は請求できないため、本籍地のある役所を訪れる交通費や郵送してもらう場合の郵送費が必要になります。
1通あたりの手数料は大きな金額ではないですが、相続人が複数いる場合や不動産が複数の地域に点在している場合など財産や相続の状況によって必要書類や必要数は変化し、総額が高くなります。
登録免許税

相続登記をするためには、登録免許税の支払いが必要です。登録免許税は、不動産の登記や自動車の登録などに必要な国税です。相続登記の登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。(※贈与の場合は固定資産税評価額の2%)
固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書に記載されている「課税証明書」や、固定資産税評価証明書で確認することができます。
土地や建物の正確な評価額を調べて、事前に準備しておきましょう。登録免許税を支払うタイミングは登録申請時です。
司法書士の報酬
司法書士の報酬は、5~15万円程度かかるのが一般的です。司法書士の報酬には登記手続きだけでなく、法的なアドバイスや書類作成サービスが含まれることもあります。地域や相続の複雑さでも報酬は変化するので、事前に複数の司法書士から見積もりを取るのがおすすめです。
司法書士によっては、時間単位で費用を設定している場合もあるので、見積もりの際に確認しましょう。
司法書士に相続登記を依頼するメリットやポイント

相続登記の手続きでは、信頼できる司法書士を選ぶことが重要です。司法書士に相続登記を依頼する場合、以下の点を考慮しましょう。
- 司法書士に依頼するメリット
- 司法書士を選ぶポイント
司法書士に依頼するメリット
司法書士に手続きを依頼するメリットは以下のとおりです。
- 手続きの正確性が保証される
- 時間と労力を節約できる
- 法律や税金について適切なアドバイスが得られる
- 法的なトラブルや将来の紛争を未然に防げる
- 書類の提出ミスや期限を過ぎるリスクを減らせる
司法書士を選ぶポイント
司法書士を選ぶ際は、以下のポイントを確認しましょう。
- 経験年数と実績
- 相続登記に関する専門性や知識
- 事前の相談時の対応や説明の明確さ
- 料金体系の明確さ
- 評判や口コミ
- 対応地域
- 相続登記以外の法務サービス
相続登記を司法書士に依頼することで、複雑な手続きを安心してスムーズに進められます。
相続登記の費用を節約する方法

相続登記の費用を節約するには、適切な知識と準備が必要です。費用を節約するには、以下のポイントを押さえましょう。
- 相続登記の費用を節約する方法
- 節約の具体的な効果
相続登記の費用を節約する方法
相続登記の費用は、複数の方法を組み合わせることで大幅に節約できます。相続登記の費用を節約する方法は以下のとおりです。
- 必要書類を正確に把握して余計な手続きを省く
- 必要書類を自分で集める
- 複数の司法書士から見積もりを取る
- 簡単な案件であれば自分で登記手続きをする
相続手続きの一部のみを依頼し、司法書士の報酬を減額させる方法もあるので、「自分でできることは自分で準備をして費用を抑えたい」という人は司法書士に依頼する際に交渉してみましょう。
節約の具体的な効果
効率的に節約すれば、相続登記の費用は全体コストの10~20%程度を削減できます。節約による具体的な効果は以下のとおりです。
- 高額な専門家費用の削減
- 遅延料金や追加料金の発生の予防
- 長期における財産管理の効率化と資産の保全
相続登記の費用の節約はすぐに実感できる利益だけではなく、将来的な資産運用にも良い効果をもたらします。
相続登記の費用に関するよくある質問

相続登記の費用に関するよくある質問について解説します。
- 誰が費用を負担するの?
- 相続登記を怠った場合は?
- どのような場合に費用が増えるの?
- 相続登記を司法書士に依頼した方が良いケースは?
- 相続登記にかかる費用は経費になる?
誰が費用を負担するの?
相続登記の費用は、法律で特に負担者の取り決めがないため、相続人が共同で負担するのが一般的です。全員で均等に分担するのが基本ですが、相続人の間で合意があれば、分担比率を変えられます。特定の相続人が費用を前払いして、他の相続人からそれぞれの負担額を回収する方法も可能です。
費用の負担について、相続人の間で合意形成できない場合は、法律の専門家へ相談することをおすすめします。
相続登記を怠った場合は?

相続登記を怠った場合、以下の問題が発生するおそれがあります。
- 相続財産の管理や取引が困難になる
- 第三者による不正な登記のリスクが高まる
- 法定相続情報一覧図の提出が必要になる
- 相続税の申告で必要な評価が難しくなる
- 将来的に相続争いの原因となる
相続したことを知った時から3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、10万円以下の科料が科せられる可能性があります。
トラブルを防ぐためにも、相続が発生した際は速やかに相続登記をしましょう。
どのような場合に費用が増えるの?
相続手続きでは、以下のように費用が増加するケースがあります。
- 複数の相続人が存在し、調整が必要である
- 相続財産の状況が複雑である
- 相続に異議を唱える関係者がいる
- 法的な争いが発生した
- 弁護士や司法書士のアドバイスや代行が必須である
- 相続税がかかる
- 海外に資産がある
複数の要因が生じると、費用が増加します。それぞれのケースにおける問題を理解し、適切な対応を計画することが重要です。
相続登記を司法書士に依頼した方がいいケースは?
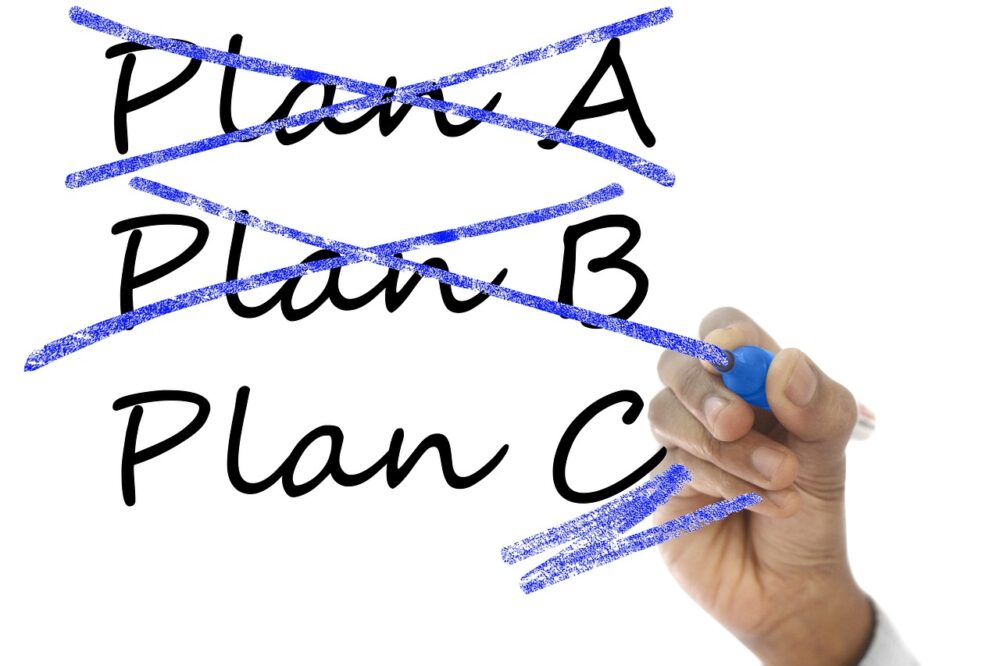
相続登記を司法書士に依頼した方が良いケースは以下のとおりです。
- 不動産の相続手続きが複雑である
- 相続人間でトラブルが予想される
- 相続人に未成年や成年後見人が含まれている
- 法的な知識に自信がない
- 海外在住の相続人がいる
専門的な知識が必要な場合、複雑な手続きへの対応や中立的な立場での判断が必要な場合は司法書士に依頼しましょう。依頼することで、難しい手続きをスムーズに進められます。
相続登記にかかる費用は経費になる?
経費として計上できるのは、事業に直接関係のある費用に限られます。個人が相続により不動産を取得した場合、かかった費用は経費として認められないのが一般的です。相続登記は私的な資産の所有権変更に関わるもので、事業に関わるものではないからです。
以下のケースであれば、相続登記の費用が経費として認められます。
- 事業用として不動産を相続する
- 法人が相続で不動産を取得した
相続登記の費用の取り扱いはケースによって異なるので、税理士など専門家のアドバイスを受けましょう。
相続登記を自分で行うメリット

相続登記を自分で行うメリットは以下のとおりです。
- 費用を節約できる
- 手続きを理解できる
- 個人情報を他人に渡す必要がない
費用を節約できる
相続登記を自分で行うことの最大のメリットは、費用を節約できることです。自分で手続きを行うことで、必要な費用が申請料や登録免許税のみに限られます。
以下の費用も節約できるので、全体の費用をより抑えることが可能です。
- 弁護士や司法書士への依頼にかかる費用
- 不要な付随サービスの費用
- 複数の相続において各専門家への依頼にかかる費用
手続きを理解できる

相続登記を自分で行うことのメリットは、手続きについて深く理解できることです。
- 法律や不動産登記への理解が深まる
- 法律的な事案に対応できる基礎知識が身に付く
- 登記における必要書類の収集方法がわかりトラブルを防げる
相続登記を自分で行うことで、将来的に直面する可能性がある問題へ対処する準備が整います。
個人情報を他人に渡す必要がない
相続登記を自分で行えば、個人情報を他人に渡す必要がありません。プライバシーが保護され、情報が外部に漏れるリスクを大幅に低減できます。
相続登記を自分で行うデメリット
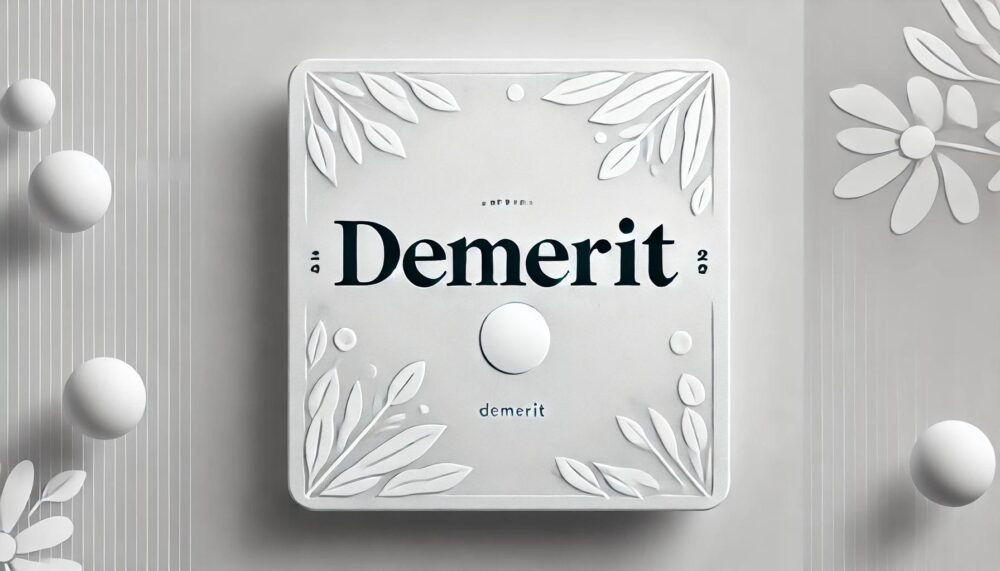
相続登記を自分で行うでデメリットは以下のとおりです。
- 法的な知識が必要である
- 時間と労力がかかる
- ミスやトラブルが発生するリスクがある
法的な知識が必要である
相続登記を自分で行う際には、以下の分野に関する法的な知識が必要です。
- 相続法
- 所有権移転に関する法律
- 税法
書類の作成能力やリスク管理の知識も欠かせません。専門家に依頼しない分、法的な知識を自分で勉強する必要があります。
時間と労力がかかる

時間と労力がかかるのが、自分で相続登記を行う際のデメリットです。専門家に依頼すれば代行してくれる以下の作業を、自分で処理しなければなりません。
- 必要書類の収集
- 書類への正確な記入と作成
- 行政機関への複数回の訪問
相続登記を自分で行う際は、かなりの時間を割く覚悟が必要です。
ミスやトラブルが発生するリスクがある
ミスやトラブルが発生するリスクがある点も、自分で相続登記を行うデメリットです。相続登記の手続きでは、書類の準備や記入において、正確さが求められます。
1つのミスから、以下のトラブルに発展することも珍しくありません。
- 将来の売却や再登記時にトラブルが発生する
- 相続人の間での紛争から法的トラブルへ発展する
- 税金の計算ミスから追加徴税が発生する
相続登記では将来の法的な問題や経済的な損失の発生を防ぐために、正確に手続きを進めることが求められます。
まとめ

相続登記は遺産相続の際に必要な手続きです。不動産の法的な所有者を明確にし、トラブルの発生を防ぐために、2024年4月から実施が義務付けられました。相続登記の手続きにはさまざまな費用が必要で、財産や相続の状況によって金額は変動します。
自分で書類を集めたり、複数の専門家から見積もりを取ったりすることで、費用の節約が可能です。相続登記を怠ると、不動産の売却や新たな登記が困難になるリスクがあります。期限内に相続登記の手続きを済ませましょう。