※記事内に広告を含む場合があります

空き家問題は深刻な社会問題であり、多くの人が相続した実家の処分に頭を悩ませています。空き家の売却を後押しする、空き家特例を活用するのは一つの手です。この記事では、空き家特例の基礎知識や適用条件、申請方法を解説します。
記事を読めば、空き家特例を活用して相続した空き家を有効に処分する方法がわかります。空き家特例では、相続した空き家を売却する際の譲渡所得税の大幅な軽減が可能です。適用には一定の条件があるため、空き家特例の概要をよく把握したうえで、適切に活用しましょう。
空き家特例の基礎知識

空き家特例の基礎知識として、以下を解説します。
- 空き家特例の概要
- 空き家特例の対象物件
- 空き家特例の税制上のメリット
空き家特例の概要
空き家特例は、相続した空き家を売却する際に受けられる税制上の優遇措置です。活用すると、譲渡所得税と個人住民税の軽減が可能です。相続した空き家を売却する際、譲渡所得から3,000万円を特別控除できます。空き家特例を活用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 相続日から3年以内に売却すること
- 被相続人の居住用家屋および敷地であること
- 耐震リフォームを実施すること
空き家特例は空き家の有効活用と流通促進を目的としており、相続人にとってメリットの多い制度です。
» 【初心者向け】空き家を売却するメリットと売却する方法を徹底解説!
空き家特例の対象物件

空き家特例の対象物件は、被相続人の居住用家屋と敷地です。昭和56年5月31日以前に建てられ、現在の耐震基準を満たしている、耐震改修を行った家屋である必要があります。相続の直前に被相続人が住んでおり、被相続人以外の人は住んでいなかったことも条件です。事業や貸し出しに使用している場合は対象外です。
空き家特例の税制上のメリット
空き家特例では、譲渡所得から3,000万円の特別控除が適用されます。相続税評価額よりも高額で売却した場合の税負担の軽減が可能です。耐震リフォーム費用の負担も軽減できる場合もあります。空き家特例は、早期売却の促進にも効果的です。相続人は経済的な負担を軽減しつつ、社会的な空き家問題の解決に貢献できます。
空き家特例の適用条件

空き家特例の適用条件は、以下のとおりです。
- 相続した居住用家屋であること
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- 現行の耐震基準を満たす状態にして売却すること
- 他の適用条件
相続した居住用家屋であること
相続した居住用家屋であることの要件として、以下を満たす必要があります。
- 被相続人が居住していた家屋であること
- 相続により取得した家屋であること
- 事業や貸付けに使用されていないこと
- 相続人自身が居住していないこと
- 相続開始から3年以内に譲渡すること
特例の適用を受けるためには、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡が必要です。
昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること

空き家特例は、建築基準法の新耐震基準導入前の建物が対象です。昭和56年6月1日以降に建築された家屋は対象外となるため、建築年月日をしっかり確認しましょう。建築年は、固定資産税評価証明書などの公的書類で確認できます。築40年以上の古い家屋は、耐震診断や耐震改修が必要な場合があります。
リフォームや増改築歴がある場合は、適用の条件が変わるケースがあるため注意が必要です。建て替えた場合は、対象外となる可能性もあります。空き家特例の適用条件は複数あるため、すべての条件を漏れなく確認することが大切です。
現行の耐震基準を満たす状態にして売却すること
空き家特例を適用するためには、現行の耐震基準を満たす状態にして売却する必要があります。手順は以下のとおりです。
- 耐震診断を依頼する
- 耐震改修計画を策定する
- 耐震改修工事を行う
- 検査をする
- 証明書を取得する
耐震改修工事の費用は売主負担となるため、事前に予算の確認をしましょう。工事の内容や費用は物件によって異なるため、専門家のアドバイスを受けてください。耐震基準適合証明書の有効期限は診断の実施日から通常2年間です。売却前に証明書を取得し、有効期限内に売却を完了させましょう。
他の適用条件

空き家特例を適用するには、以下の条件も満たす必要があります。
- 売却価格が1億円以下であること
- 都市計画区域内の土地であること
- 建築基準法に適合していること
- 一定規模以上の土地であること
相続人が複数いる場合、売却には全員の同意が必要ですが、各相続人が要件を満たせば、それぞれ特例を適用できます。空き家特例を適用する際は条件を事前によく確認し、不明な点があれば専門家に相談しましょう。
令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡で、相続人が3人以上の場合、各相続人の控除上限額は2,000万円となることも覚えておきましょう。
空き家特例の申請方法

空き家特例の申請方法は、以下のとおりです。
- 売却する物件が特例に該当するか確認する
- 必要書類を準備する
- 物件売却後に確定申告する
売却する物件が特例に該当するか確認する
売却する物件が特例の条件を満たしているか確認するためのポイントは、以下のとおりです。
- 建築年月日
- 賃貸利用状況
- 耐震基準
- 売却期限
- 売却先
- 土地面積
条件を確認する際は、税務署や不動産業者への相談をおすすめします。専門家のアドバイスによる適切な判断が可能です。耐震基準の確認も重要なので、耐震診断を実施します。現行の基準を満たしていない場合は、改修工事の検討が必要です。
必要書類を準備する

空き家特例を申請する際の必要書類には、以下が挙げられます。
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続関係図
- 遺産分割協議書
- 登記簿謄本
- 固定資産税評価証明書
- 耐震基準適合証明書
- 売買契約書の写し
- 譲渡所得の確定申告書
- 居住用財産の譲渡所得の特別控除申告書
- 被相続人の住民票除票
- 相続人の住民票
相続や物件の状況を証明するための書類が求められます。書類の準備には時間がかかる場合があるため、早めに取りかかりましょう。不明点は、税務署や専門家に相談してください。
物件売却後に確定申告する
物件売却後は、確定申告をする必要があります。確定申告書を作成し、必要事項を記入します。譲渡所得の内訳書と空き家の譲渡所得の特別控除に関する明細書の作成も必要です。確定申告書に耐震基準適合証明書や登記事項証明書などの書類を添付し、税務署に提出します。
申告期限は、物件を譲渡した年の翌年の2月16日から3月15日までです。期限を過ぎないよう注意しましょう。確定申告はe-Taxを利用した電子申告もできます。
空き家特例が適用されないケース

空き家特例が適用されないケースは、以下のとおりです。
- 賃貸利用した場合
- 非居住用の家屋の場合
- 相続開始から3年を超えて売却した場合
- 売却先が法人の場合
賃貸利用した場合
空き家特例の目的は空き家の有効活用と流通促進にあるため、賃貸利用した物件は適用の対象外です。一時的な賃貸でも、賃貸履歴があれば特例が適用できない可能性があります。賃貸利用した物件の売却には、通常の譲渡所得税が課税されます。
賃貸利用の期間や状況によっては個別判断が必要な場合もあるため、専門家への相談がおすすめです。相続後の賃貸利用を検討する際は、将来的な売却計画も考慮に入れましょう。賃貸利用は空き家の有効活用の一つの方法ですが、空き家特例の適用を希望する場合は売却が適しています。
非居住用の家屋の場合

以下の非居住用の家屋には、空き家特例が適用されません。
- 事務所や店舗
- 一度も居住用として使用されていない家屋
- 相続前に非居住用として使用していた家屋
建物の一部が非居住用だった場合は、該当部分のみ特例の対象から除外されます。非居住用から居住用に用途変更した場合は、原則として特例が適用できません。非居住用の家屋を相続した場合は、他の税制優遇措置の適用を検討することがおすすめです。
相続開始から3年を超えて売却した場合
空き家特例では、相続開始から3年を超えて売却した場合は適用できません。ただし、相続時から3年経過後に耐震リフォームを行い、完了から2年以内に売却した場合は例外として期間外の適用が可能です。リフォーム後は相続時の耐震性能は問われません。
相続後3年以内の売却が難しい場合は、耐震リフォームの実施を検討できます。耐震リフォームを行えば、物件の価値が上がるメリットも得られます。リフォームにかかる費用を確認し、費用対効果を十分に考慮しましょう。税制や不動産市場の状況は変化するため、最新の情報を確認することも大切です。
売却先が法人の場合

空き家特例は個人への売却が条件であり、売却先が法人の場合には適用されません。法人への売却を行った場合は、通常の譲渡所得税と住民税の課税対象になります。親族が経営する法人への売却の場合も同様です。空き家特例を利用するためには、売却前に買主の属性を確認しておくことが大切です。
空き家特例を申請する際の注意点
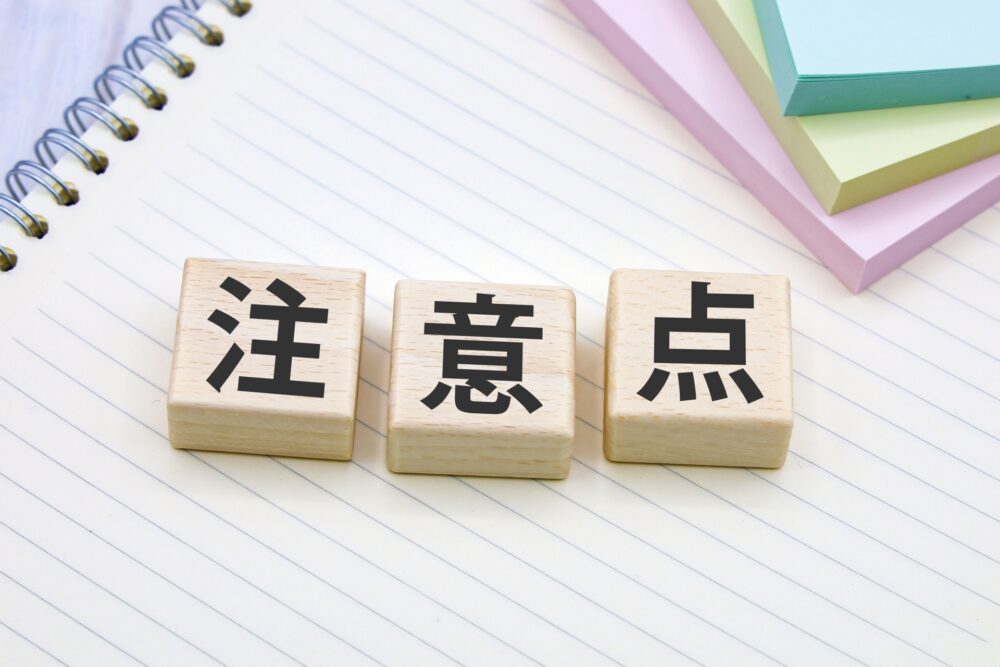
空き家特例を申請する際は、以下の点に注意しましょう。
- 耐震基準を満たすための改修費用が発生する場合がある
- 他の税制優遇と併用できるか確認する
- 適用条件を事前に確認する
耐震基準を満たすための改修費用が発生する場合がある
古い家屋は現行の耐震基準を満たしていない場合が多いため、空き家特例の申請前に耐震診断を行います。結果基準を満たしていない場合は、改修工事が必要です。耐震改修工事にかかる費用は、家屋の状態や規模によって大きく異なります。工事の規模によって数百万~数千万円に及ぶ場合があります。
改修費用が物件の価値を上回る場合は、特例適用のメリットが薄れる可能性があるため注意が必要です。耐震改修に関する補助金や税制優遇制度を利用できる場合は、費用の負担を軽減できる可能性があります。改修工事中は物件を売却できないため、タイミングも重要です。工事期間を考慮して売却計画を立てましょう。
他の税制優遇と併用できるか確認する

空き家特例は、以下の制度との併用ができます。
- 居住用財産の3,000万円特別控除
- 特定居住用財産の買換え特例
- 認定住宅の新築等の所得税額の特別控除
- 住宅ローン控除
- 譲渡損失の繰越控除
- 相続時精算課税制度
- 譲渡所得の配偶者控除
複数の特例を組み合わせれば、税負担をより軽減できます。各制度には適用条件や期限があるため、個別に確認しましょう。専門家のアドバイスを受けると、自分の状況に合った税制優遇の活用方法が見つけられます。
適用条件を事前に確認する
空き家特例を適用する際は、事前に以下の条件を確認しましょう。
- 相続した物件が空き家特例の対象となるか
- 建築年月日が昭和56年5月31日以前か
- 耐震基準を満たしているか
- 改修が必要か
- 相続開始から3年以内に売却可能か
- 売却先が個人であるか
必要書類のリストを作成し、計画的に準備すると手続きがスムーズです。申請期限や手続きの流れも事前に把握しておきましょう。
空き家特例に関するよくある質問

空き家特例に関する以下のよくある質問に回答します。
- 被相続人が老人ホームに入居していた場合でも空き家特例の適用は可能か?
- 空き家特例の適用期間はいつまでか?
- 複数の相続人がいる場合でも空き家特例は適用される?
被相続人が老人ホームに入居していた場合でも空き家特例の適用は可能か?
被相続人が老人ホームに入居していた場合でも、空き家特例の適用は可能です。老人ホームの入居に関しては、特例を柔軟に適用する仕組みが整えられています。適用条件として、老人ホーム入居前に被相続人の居住用財産であったことが求められます。入居後に事業用や賃貸用として使用されていないこともポイントです。
空き家特例の適用期間はいつまでか?

空き家特例の適用期間は、令和9年12月31日まで延長されています。個々の適用期間は、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却が対象です。期限を過ぎないよう、早めに売却計画を立てましょう。特例の期間や条件は法改正により変更される可能性があるため、最新の情報の確認も大切です。
複数の相続人がいる場合でも空き家特例は適用される?
複数の相続人がいる場合でも、空き家特例は適用可能です。譲渡益に対する控除は、相続人間で分割して計算されますが、それぞれの相続人が特例の恩恵を受けられます。令和6年以降は、相続人が3人以上の場合に控除額が2,000万円に減額される新たなルールが適用されます。
複数の相続人が関わる場合は、事前に売却計画を話し合い、全員が合意する形で手続きを進めることが大切です。売却後の確定申告は、相続人それぞれが正確な情報を申告する必要があります。手続きを確実にするためには、税理士への相談がおすすめです。
まとめ

空き家特例は、相続した古い家屋を売却する際に税制優遇を受けられる制度です。特例を活用すると、相続した空き家の処分がスムーズに進められます。空き家特例の適用は、昭和56年5月31日以前に建築された居住用家屋が対象です。現行の耐震基準を満たす状態で売却することも条件の一つです。
相続開始から3年以内に個人へ売却することも求められます。賃貸利用した物件や法人への売却は適用外であり、注意が必要です。申請時は、書類の準備や確定申告などの手続きを行います。空き家特例を利用する際は、適用条件の事前確認が大切です。特例を上手く活用し、相続の経済的な負担を軽減しましょう。
» 空き家問題を解決!適切な管理をして上手に活用する方法を解説